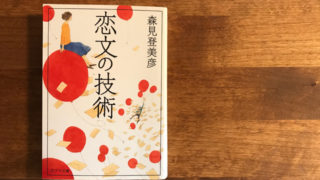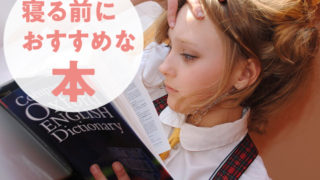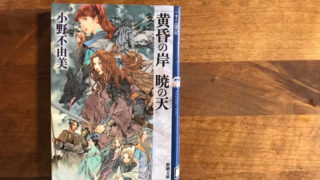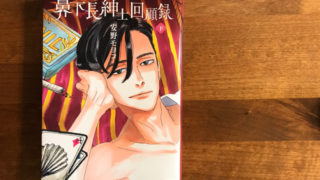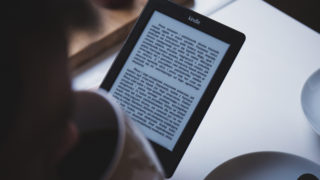時には映画の話でも。
昨日観たのはNetflixオリジナル作品の「バスターのバラード」という映画。
特に観たいものもなく、ぶらぶらと登録映画欄を見ているうちに発見したこの作品。
監督がコーエン兄弟なのと、6つの短編からなるオムニバス、そして西部劇が部隊という点で観ることにきめました。
何の気なしに見はじめましたが、これがなかなかブラックユーモアが効いていて面白かった。
本日はコーエン兄弟の新作(2019年現在)短編西部劇オムニバス「バスターのバラード」の紹介とその感想を記したいと思います。
※一部ネタバレ含みます
【感想】「バスターのバラード」悲惨さとブラックユーモア西部劇
映画監督「コーエン兄弟」の作品はかっこいい
「コーエン兄弟」とはジョエル・コーエン、イーサン・コーエンの兄弟からなる映画監督。
私の感想として、その作風は「かっこよさとブラックユーモアが効いているけど、よくわからないところもある。」です。
私的にコーエン兄弟で一番好きなのは「ノーカントリー」ですね。サイコっぽさもある殺し屋役のハビエル・バルデムがなんともかっこいい。ハードボイルドながら、哲学めいた雰囲気も漂うドライな作品。
「バーバー」なんかも、映像はかっこいいのに、展開はドライで皮肉めいていてその雰囲気が好きです。でも、映像や展開は好きだけど、どうもよくわからない、もやっとした部分も併せ持つ作風。
わかりやすい映画がもてはやされる時代ですが、コーエン兄弟のような、何かもやっと考えさせられる映画も刺激(?)になっていいもんです。
そんなコーエン兄弟の「バスターのバラード」ですが、私的には今まで見た監督の作品の中で「ノーカントリー」に次ぐ面白さでした。
「バスターのバラード」西部開拓時代に起こる、6つの短編オムニバス映画

「バスターのバラード」は表題の短編を含めた6つの話からなるオムニバス映画。
ただ、いわゆる拳銃でどんぱちするような西部劇の話は「バスターのバラード」と二作目の「アルゴドネス付近(銀行強盗でヘマをやらかす男の話)」でしょうか。
銃撃戦やアクションでみせるというよりも、人生の悲哀や悲惨さなんかのほうが強く描かれたように感じます。ただ、その悲哀をウェット状態で描くわけではない。
「バスターのバラード」、コーエン兄弟による西部劇、6編のオムニバス。強い奴は死ぬ。弱い奴も死ぬ。悪い奴は生き残る。「男は「手を見たならその手でやれ」と鼻であしらった」「アーサーはビリーナップに合わせる顔がない」短編の副題の意味が最後で分かって面白かった。 pic.twitter.com/5qJVFOmlec
— まこたん (@mktn1006) February 27, 2019
「悲哀や悲惨」なんて書くと「えっ、重ーい気分になる映画なんじゃ無いの?」と思われるかもしれませんがさにあらず。
全体的に登場人物は悲惨な感じなんだけど、重く、暗くならないようなドライなブラックユーモアが随所に感じられ、落ち込むという感じではありません。
悲惨さとブラックユーモアが見事にマッチ

表題の「バスターのバラード」を1本目に持ってきているのもいい感じ。6つの短編の中では、一番アクション風味が強い、西部劇らしい作品。
ただ、とにかくあっけない終わりかた。「えっ?これで終わり???」とあっけにとられる感じ。
人の生き死にに関係する内容ですが、ドライなブラックユーモアが効いており、これを一発目に持ってこられることで、この後のどの作品も「こういうテイストなんだな」という覚悟で観てしまう自分がありました。
へんな話、ある種の安心感と言いましょうか。一本目の「バスターのバラード」を観ておくと、後の作品で悲惨な展開が訪れようとも「救われることは無いだろうな」というよくわからない安心感。
「助かるか?助からないか?」のドキドキはなく「この登場人物は今悲惨な目にあっているけど、おそらくブラックユーモアの効いた終わりかたで、きっと救われることは無いだろう」という安心しきった感じで展開を楽しむことができたのです。
唯一救い(?)のある話は、4本目の「金の谷」だけ。救いといおうか、悲惨な終わりかたではなかったというはなし。
「金の谷」の緊張感(ネタバレ含む)!
「金の谷」はシンプルっちゃあシンプルな話。金鉱を見つけにきたじいさん。
あっちこっち掘って、穴の中でようやく金脈を見つける。っと後ろから銃で撃たれる。若い男が、そのじいさんをずっと付け狙っていたのでした。
若者は穴の外でじいさんの様子を見る。どうやら死んでいるようなので、穴の中へ。
どっこい、死んでなかったパワフルじいさん!若い男を返り討ち。逆に殺してしまいます。
じいさんは背中から撃たれたものの、弾丸は貫通し、なおかつ致命所ではなかったため、無事金塊を手にして帰っていくのでした。
この「金の谷」が、私的に一番のヒットでした。若者がじいさんが死んだか死んでいないか、穴の外でじっと待つシーンの緊張感がなんとも言えずかっこいい。
穴の外で、紙巻きタバコを震える手で作り、火をつける若い男。その紙巻きタバコに一瞬目をやった瞬間に、じいさんが襲ってくるんじゃないかという、緊張感がしばらく続きます。
その金鉱のある場所が、とても綺麗な小川のある原っぱ、大自然の中だけに、そのシーンの妙に緊迫した空気感と清々しい風景のギャップがたまりませんでした。
悲惨なのは「食事券」と「早とちりの娘」
「バスターのバラード」の中で悲惨なのは「食事券」と「早とちりの娘」

「食事券」は四肢の無い旅芸人の男と、その男を使って金稼ぎをする初老の男の話。物語が進むにつれて、だんだんと芸人の男に客がつかなくなる。そんな中、初老の男が見つけた、計算をするにわとり。男はそれを買う。
荷馬車の中でにわとりとゆられる旅芸人の男。荷馬車は、真冬の橋のそばを通りかかる。初老の男は、橋の上から石を落として川の深さを確かめる。深さを確認して、旅芸人に近づく初老の男。次のシーンでは、荷馬車にはにわとりだけに。
「早とちりの娘」は悲惨というよりもブラックユーモアがたっぷり効いた話。キャラバンとともに旅中の娘。うっかり、その隊列を離れてしまいます。キャラバン護衛の男が娘を迎えに行く。娘を発見し、帰ろうとした時、遠くからインディアンがこちらに襲ってくる。
護衛の男は娘にピストルを渡し「もし俺が死んだら、それで自分自身を撃ちぬけ。悲惨な目にあいたくなければな」と。
複数のインディアンとの戦い。護衛の男は、インディアンに不意を打たれ倒れこみます。頭の皮を剥ぎにくるインディアン。しかし男は死んだふりをしていただけ。インディアンを撃ち、見事集団を撃退します。
しかし、これがよくなかった。護衛の男の死んだふりを、本当に死んだと早とちりした娘は、自分の眉間を撃ち抜いていたのでした。
「食事券」も「早とちりの娘」も悲惨な結末。しかし、決して重たい空気感にはならないのはコーエン兄弟の技量のなせる技でしょう。特に「食事券」など救いようのない話ですが、さっぱりとした印象も。旅芸人の男と初老の男の間に会話が描かれず、ふたりの仕草や表情で互いへの思いを読み取る構成が、そんな印象を抱かせたのかもしれません。
全部見せない、観客に想像の余地を十二分に持たせる。その余地、余白の部分にドライな空気がないまぜになり、この独特の感覚を覚えるのかなとも思いました。
一貫してドライ。ウェットな空気感の排除。

悲しみや哀しみはどちらかというとウェットな感情のように思います。
この「バスターのバラード」では、そういったウェットな部分を、展開や映像でとことん排除し、一貫してドライな空気感を作り上げていたような感想を持ちました。
そのドライな空気感にブラックユーモア(皮肉)がうまいこと乗っかって、悲惨を悲惨とも感じずないように仕向けているのです。
「バスターのバラード」で描かれているのは人生の悲哀ともとれることですが、そこにウェットさはないので、さらりと観ることができました。
けっこうわかりづらい部分なんかもありましたが、その辺のもやっと感も含めてコーエン兄弟らしさの感じる、ちょっと変わった西部劇でありました。
※惜しむらくは、この「バスターのバラード」はNetflix限定なので、レンタルビデオ店やアマゾンプライムなどで見れないところ。どうしても観て見たい方は、Netflixご登録をば。
【関連記事】:「はじまりへの旅」普通とは何か?多様性について考える映画